ここから本文です。
みやぎ食育表彰
宮城県では、保育所、学校、地域などで食育活動に積極的に取り組み、県民の健康増進、みやぎの食文化の伝承などの分野においてめざましい功績を挙げられた方々を表彰する「みやぎ食育表彰」を実施しています。
令和7年度の受賞団体NEW!
「みやぎ食育大賞」加藤真崇氏
加藤真崇氏は、特別史跡多賀城跡の敷地内遺跡の水田において、多賀城古代米「おくのむらさき」を栽培し、市内全小学校5年生を対象に田植え・稲刈り・調理実習を通じて郷土の歴史や食文化を学ぶ「古代米学習プログラム」を展開している。活動は、農家・学校・行政・地域団体が連携して平成28年度から継続しており、学校給食での提供や地域の誇りの醸成など、多賀城市全体に広がる取組となっている。
本取組は、長年にわたり地域一体で実践され、歴史・文化・農業を融合した創意工夫に富む活動として実践されていることや、子どもから大人まで広がる食育となっていることが評価され、受賞となった。

「みやぎ食育奨励賞」相澤充氏
相澤充氏は、漁業士として、石巻のノリ養殖業を営みながら、地域の小学生を対象に、ノリ養殖の体験活動、出前講座などを実施し、地域食材の「ノリ」やノリ養殖業の魅力発信を積極的に行い、石巻の水産業への関心を高めている。また、東日本大震災の被災により一時は廃業を考えたものの、周囲の励ましや日本各地からの支援により、ノリ養殖業の再開に踏み切った決意とノリ養殖業を続ける意義について、自身の経験を伝えている。
本取組は、地元水産業への関心を高める活動や食に対する感謝の心を育む活動、さらに東日本大震災の教訓などの伝承活動を長年にわたり継続していることが評価され、受賞となった。

「みやぎ食育奨励賞」東松島市立矢本東小学校
東松島市立矢本東小学校は、学校行事、委員会活動、地域との協同の学び、放課後活動等あらゆる場面において、多様な主体と連携し、それぞれの学年に応じた「食を通じた体験型の学び」に積極的に取り組んでいる。また、デジタルを取り入れた食育活動にも積極的に取り組んでおり、児童が調べたことをもとに作成した食育クイズを市が配信しているサイト内で公開するなど、その活動は学校だけにとどまらず、地域に向けた情報発信ともなっている。
本取組は、多様な主体との連携により、創意工夫して積極的に食育に取り組んでいることや、地域へ波及する取組を行っていることが評価され、受賞となった。

令和6年度の受賞団体
「みやぎ食育大賞」高舘食道水神蕎麦
高舘食道水神蕎麦は、自ら手打ちしている宮城県産そば粉を用いたそばの提供により、その魅力や奥深さを消費者に発信し続けている。その傍ら、そば打ち体験を随時受け入れ、作る楽しみを体感する機会の創出にも注力している。
また、「食」のプロとして次代を担う子どもたちに食の魅力を伝える『食材王国みやぎ「伝え人(びと)」』に登録し、そば打ち体験では参加者が楽しみながら食の魅力を実感できるよう工夫することで、実践的な食育活動を展開している。併せて、生産者の想いを伝えることで、食材への理解と感謝の気持ちの醸成に寄与している。
本取組は、体験活動を通じて「見て」「触れて」「楽しんで」「調理して」「食べる」という、五感を使って食を実感できる取組を継続的に行っていることが評価され、受賞となった。

「みやぎ食育奨励賞」仙南栄養士会
仙南栄養士会は、仙台大学等が主催する「東北こども博」に参加し、旬の野菜当てクイズや1日に必要な野菜計量体験等の体験型の取組を行う「野菜をもっと食べようキャンペーン」を継続的に実施している。この取組は、子どもに野菜を食べることの大切さを伝えることや、親である働き盛り世代にも野菜の必要性と望ましい摂取量を伝える効果的な機会となっている。
また、各会員施設においては、料理や食品に含まれる食塩量の展示や減塩レシピの発行、減塩商品の体験や給食での減塩調味料の使用等を行い、給食提供の機会を活用し年間を通して減塩の普及啓発活動を実施している。
本取組は、食に関する知識や判断力を身につけ、それを自ら実践できるよう、体験等を通じて、健やかな心身を育む食育に継続的に取り組んでいることが評価され、受賞となった。

「みやぎ食育奨励賞」
東北生活文化大学スポーツ栄養・地域活性化プロジェクト
東北生活文化大学スポーツ栄養・地域活性化プロジェクトは、東北生活文化大学でスポーツ栄養を学ぶ学生が中心となり、「子どもから大人まで東北の人たちを東北の食材で元気にする」を目標に、県産食材とスポーツ栄養を組み合わせた食育活動を実践している。学生が地域に出向いて、地元食材を意識した栄養サポートや地元食材を用いた栄養講話をするなど、小中学生から成人スポーツチームまで幅広い世代を対象に活動を継続している。また、近年は、外部資金を獲得し活動資金を得ることで、プロジェクトの活動の幅を広げている。
本取組は、県民一人一人が主体的に食育に取り組むため、団体が持つ専門性や特徴を活かし、食とスポーツを活用した取組を行っていることが評価され、受賞となった。
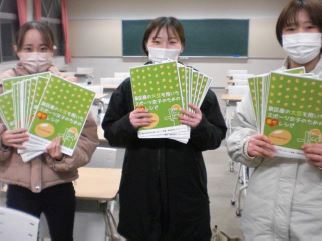
令和5年度の受賞団体
「みやぎ食育大賞」白石市立深谷小学校
白石市立深谷小学校は、県教育委員会が推奨する「ルルブル」に深谷小学校が大切にしている「ふれあい」を取り入れ、学校と家庭が連携し、生活習慣の形成と心を豊かにする取組を継続して実施しています。年8回実施している「ルルブルふれあいウィーク」の取組は、生活記録カードを活用し1週間の生活習慣を記録することで、健康に過ごすための朝食の在り方や食事の仕方について考える機会となっています。取組を家庭にフィードバックする「おたより」を活用し、全家庭の回答を掲載することで参加意識を高め、楽しみや意欲が増すように工夫しています。また、地元農家の協力で農作業体験を実施し、食に関わる地域の人々やふるさとを大切にする活動を継続していることに加え、昨年度は子供たちによるお米の店頭販売を行い、励ましや感謝の言葉に直に触れることで、食の生産や労働の達成感を味わうことができています。
本取組は、子ども自身が、健全な食生活に関する知識、技術を身に付けるとともに、家庭での食事や農業体験などの取組を通じて、食材や食文化への関心を高めていることが評価され、受賞となりました。


「みやぎ食育奨励賞」女川町食生活改善推進員会
女川町食生活改善推進員会は、中学生を対象に平成10年度から継続して女川町の地場産物を活用した魚食普及のための調理実習を実施し、これまで約500人の生徒を指導してきました。子供たちに料理の楽しさや食の大切さ、地域の食の魅力を伝え愛着形成を図る取組を積み重ねてきました。子供たちは、活動を通じ体験した内容を家庭に持ち帰り、家庭で料理の手伝いをする等、食への関心が芽生えた子が増えています。また、調理が楽しい、もっと学びたいと栄養士や調理師など食に関する職を志す子もみられています。
本取組は、組織が持つ専門性や特徴を生かし、調理体験や地域の特色ある食文化の伝承など継続的に食育を推進していることが評価され、受賞となりました。

「みやぎ食育奨励賞」西古川ずんだシスターズ
西古川ずんだシスターズは、宮城の郷土食「ずんだ」の魅力を広げるため、老若男女問わずさまざまな人々を対象にずんだもち作り教室を行っています。ずんだもち作り体験は、400年にわたり持続可能な水田農業が営まれてきた「大崎耕土」で生まれた食文化として、世界農業遺産を学ぶためのワークショップでも紹介しており、体験者からの評判が高く地域の伝統文化の伝承に大いに貢献しています。大人、子供、外国人、障がいのあるなしに関わらず、誰でもずんだもち作りを体験できるように工夫されており、観光業と連携し幅広い層に食育を波及しています。
本取組は、地域の食材を生かし、伝統料理や気候風土と結びついた、本県の特色ある食文化の理解と継承を実践していることが評価され、受賞となりました。

「みやぎ食育奨励賞」東松島市食生活改善推進員会
東松島市食生活改善推進員会は、コロナ禍で活動が縮小する時期も自己研鑽に励み活動ツールとしてデジタルを取り入れ、無料通話アプリLINEでの会員同士の情報交換や地域住民へスマートフォンを使用した資料や画像の情報提供など、非対面での新しい食生活改善活動を実践しています。また、シトラスリボンプロジェクトに賛同し、小学校の教職員や児童へ手作りリボンを寄贈することでコロナ差別や偏見防止の呼びかけとともに、健康な食生活の啓発を併せて行うなど、コロナ禍においても状況に応じた地道な活動を展開し活動の幅を広げています。
本取組は、コロナ禍においても活動を停滞させることなく、長年継続してきた活動にデジタルを取り入れ、新たな視点で食育活動を推進していることが評価され、受賞となりました。

これまでの受賞事例
これまでの受賞者一覧
受賞団体概要
- 令和4年度受賞者(PDF:446KB)
- 令和2年度受賞者(PDF:339KB)
- 令和元年度受賞者(PDF:368KB)
- 平成30年度受賞者(PDF:290KB)
- 平成29年度受賞者PDF:530KB)
- 平成28年度受賞者(PDF:294KB)
- 平成27年度受賞者(PDF:131KB)
- 平成26年度受賞者(PDF:151KB)
- 平成25年度受賞者(PDF:159KB)
- 平成24年度受賞者(PDF:367KB)
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています